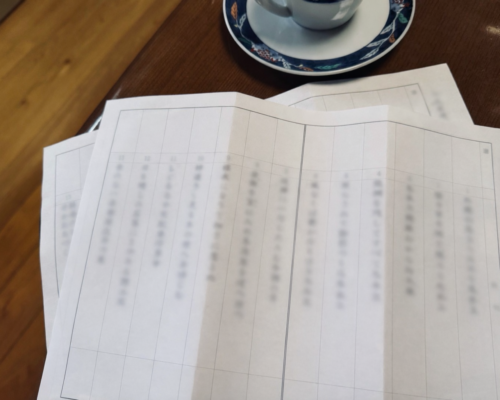私は村上市で生まれ育った。
小学生の時は歩いてまちの中心部にある大きな木造校舎の小学校に通っていた。
当時は子供の数も多く、全校生徒で1,600人くらいはいたはずだ。全校朝礼の日ともなると、講堂はいつも溢れんばかりの子供たちで埋め尽くされていた。
朝は集団登校をしていたので、いつも決まり切った通学路をみんなで歩いて学校に通っていたが、放課後は自由だった。だいたいは家が同じ方向の友だちと一緒に帰っていたのだが、時々は一人で勝手気ままにあちこち寄り道をしながら帰ることもあった。

いつだったか通学路を外れた道を歩いていると、そこに一軒の下駄屋があった。
作業場の入口は大きく開いており、その奥に気むずかしそうなおじいさんが板の間に座って仕事をしていた。
部屋の中には下駄になる木材や仕掛品などが山のように積んであり、これを全部下駄にするのは大変だなぁと子供心に思っていた。
それ以来、私はよくこの道を通るようになり、その度にこの下駄屋の作業場を覗くようになっていった。
ある日、この下駄屋の前を通ったらそのおじいさんと目が合った。
おじいさんは「よっこらしょ」と大きな声を出して立ち上がり、こちらに向かって歩いてきて、
「どこの子だ?」というので、
「かみちょう(上片町)のぬしや(塗師屋)の子です」と答えると、
「お~、げんいっつぁんとこの子だな」と表情が和らいだ。
「おめ、時々(作業場の中を)見てるみてだけど、おもっしぇか?」と聞くので、
「うん、おもっしぇ」と答えると、
「んだか、んだら、中に入って見ていくか」と作業場の中に入れてくれた。
ずらりと並んだノコギリやノミの道具類は棚の下に等間隔でぶら下がっていたが、その下に大きな木挽き用の大鋸が置いてあった。
私はこんな大きなノコギリはそれまで見たことがなかったので、
「こんなおっきいノコギリで何を切るの?」と聞くと、
「これはさ、木を切る時にこうやって使うんだども、今はもうほとんど使わのなったな」とその大鋸を軽々と持ち上げて引く格好をしてくれた。
「ここにある木材はみんなそうやっておじいさんが切ったの?」と聞くと、
「そうではねぇども、そういうのもあるな。ほれ、これなんかはそうだ」と輪切りにした桐を指差した。
それは切り口の白いきれいな丸太だった。
「ふ~ん、きれいだね」というと、
「んだろ~」とおじいさんは自慢げな表情を見せた。
「どうだ、持ってみるか?」とおじいさんは笑いながらいうので、
「うん」と返事をして持とうとしたが、とても子供が持ち上げられる重さではなかった。
「う、ははは〜!」とおじいさんはそんな私を見て高笑いをしていた。
それ以来、私は時々この作業場を覗いては、おじいさんと話をしたり、おじいさんの行う作業をじっと眺めていたりしていたのだが、ある日突然作業場の入口が閉められ、内側に白いカーテンがかかるようになり、部屋の中は一切外から見えなくなってしまった。
しばらくすると今度は、「忌中」と書かれた木の立て札が入口の脇に建った。
私はその漢字の読み方も意味も全くわからなかったが、あのおじいさんが死んだんだということだけは何となく悟っていた。
悲しいといえば悲しいことだったが、それ以上に、そこにいるのが当たり前の人が突然いなくなることもあるんだということが不思議でたまらなかった。
まちはこうやって少しずつ変わっていく。そこに誰が住んでいて、その人がどんな仕事をしていたのかもいずれわからなくなってしまう。
それでいいのだとも思うが、本当にそれでいいのかと再度自問する。まちに住む一人一人がみんな誰かにとってはとても大事な人のはずだから、忘れちゃいけないし、忘れないようにするために何かできないか、と考えてみた。
アイディアはいくつも浮かんだが、どれもこれも現実的なものではなかった。そんな簡単に素敵な答えなど出ないのだ。
やはりあのおじいさんをときどきは思い出すようにするしかないのかもしれない。